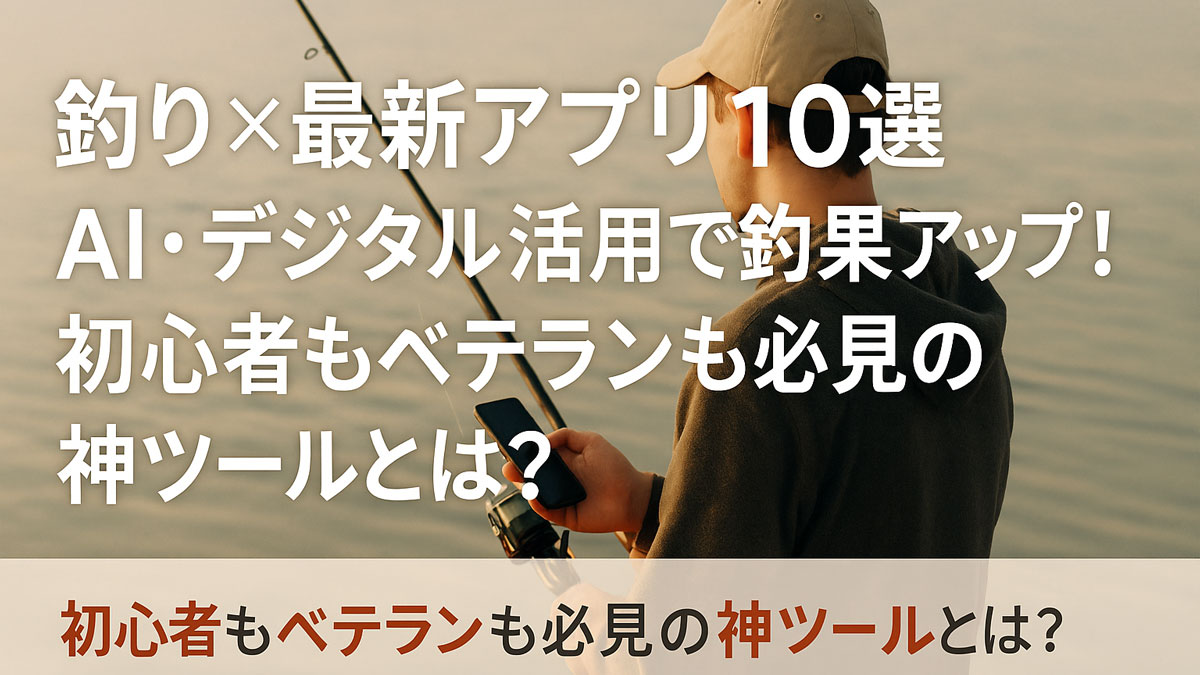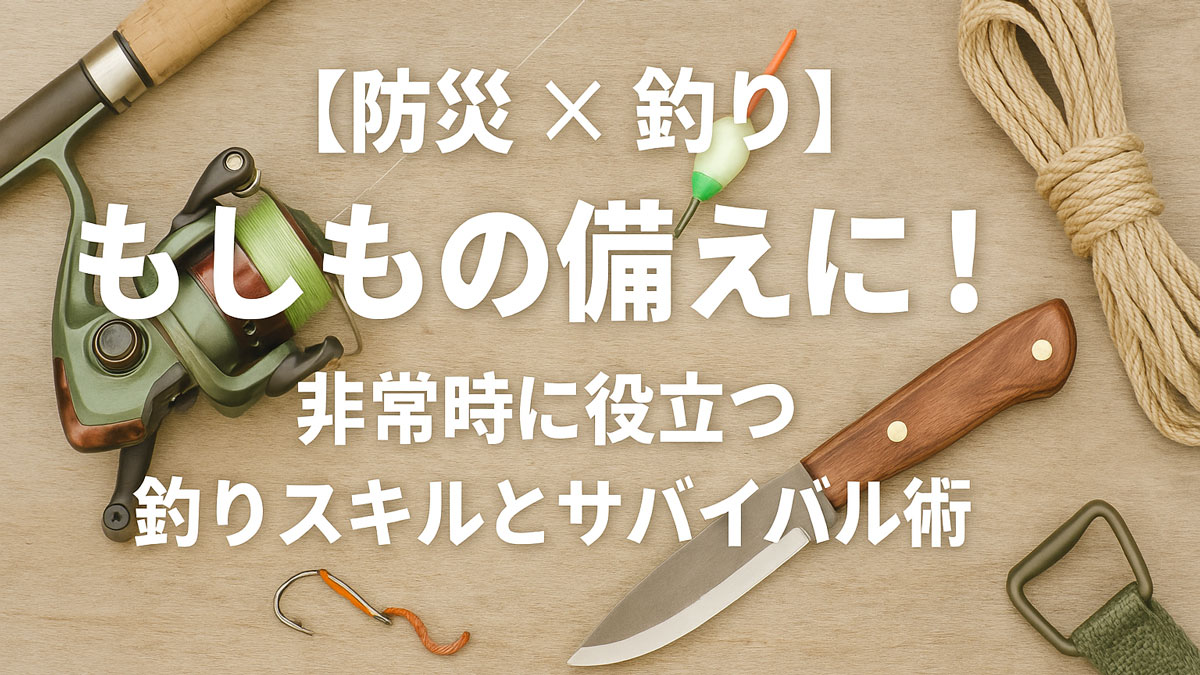
災害時に食料が不足したら、どうやって生き延びればいいの?
そんな不安を抱える方に向けて、「釣り」を防災に活かす方法を丁寧に解説します。
初心者でも実践しやすい釣りスキルや道具の選び方、安全対策まで網羅。
自然の恵みを生かして、非常時でも家族を守れる力を身につけられます。
日常の趣味がそのまま備えになる——そんな安心感を、ぜひ本記事で実感してください。
1. なぜ今「釣り×防災」なのか?|注目される理由と背景
自然災害が多発する日本では、防災意識の高まりとともに、「備える生活」が見直されています。その中で注目されているのが、「釣り」という一見レジャーに思える行動の、防災への応用です。
もしもの時に「魚を自力で捕って食べる力」や「水辺で安全に過ごす技術」は、命を守る実践的なスキルになりえます。ここでは、なぜ今「釣り×防災」が重要なのか、その背景と理由を掘り下げて解説していきます。
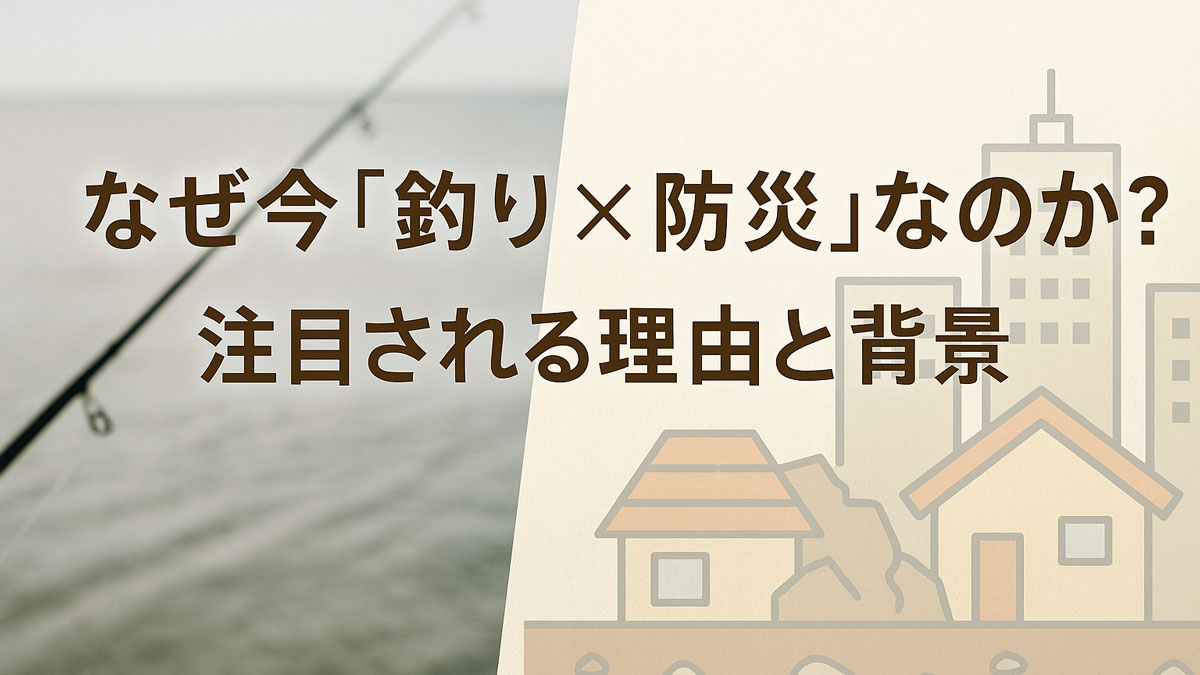
災害時に役立つ「自給自足」の力とは
災害によってインフラが途絶えた場合、食料の確保は大きな課題になります。特に河川や海に近い地域では、「釣り」が食料確保の手段として活用できる可能性があります。
例えば、停電で冷蔵庫が使えず保存食も尽きた場合でも、釣りで獲れた魚を火で炙ればその場で食事にできます。また、釣り道具の代用も工夫次第で可能です。クリップ+糸+小枝で即席の釣り竿が作れたり、ペットボトルを加工すれば簡易トラップにもなります。
こうした知識や経験は、防災マニュアルには載っていない“実践的なサバイバル力”となり、いざという時に家族や自分を守る力となります。
特に、ルアーやエサが手に入らない状況では、自然素材(貝殻、虫、パンくずなど)を代用する工夫が命をつなぎます。日常的に釣りを経験している人なら、「どこで・いつ・何が釣れるか」という地元の知識も身につくため、災害時の行動判断に差が出るのです。
都市部でも備えたい“水辺スキル”の必要性
「釣りは田舎の趣味」と思われがちですが、都市部に住む人にこそ“水辺スキル”は必要です。都市型災害では、近くの河川や運河などが避難や物資確保のルートになる可能性があるためです。
以下は、東京都内の主要釣り可能エリア(公園・水辺)と周囲の人口密集度を比較したグラフです。
【都市部における釣り可能エリアと人口密度】
| 地域名 | 釣り可能エリア例 | 周辺人口(概算) |
|---|---|---|
| 葛西臨海公園 | 東京湾岸(海釣り) | 約8万人 |
| 石神井公園 | 池釣り(ヘラブナなど) | 約12万人 |
| 多摩川河川敷 | ルアー・投げ釣り対応 | 約15万人 |
災害時にこうした水辺をどう利用するか知っているかどうかで、行動の選択肢が広がります。水辺は時に命を奪う場所にもなりかねませんが、正しい知識とスキルがあれば、逆に「命を支える資源」へと変わるのです。
また都市部では、釣りを通じて自然との接点を持つこと自体が減災教育につながります。子どもと一緒に釣りを経験することは、防災教育の第一歩にもなります。
おわりに
日常の趣味である釣りは、災害時には“命をつなぐ手段”にもなります。趣味として楽しむだけでなく、万が一に備えた知識としての釣りも、これからの防災には欠かせません。
次回は、具体的にどのような「釣りスキル」「代用釣具」「調理法」が防災に役立つのかをご紹介します。自然と遊びながら、同時に備える力も育てていきましょう。
2. 非常時に使える!基本の釣りスキル&サバイバル技術
災害時やアウトドアでの非常事態では、身の回りにあるもので食料を確保する力が問われます。中でも釣りは、水辺があれば比較的実行しやすい「自給自足術」のひとつです。この章では、非常時に役立つ実用的な釣りスキルや簡易調理法を紹介します。
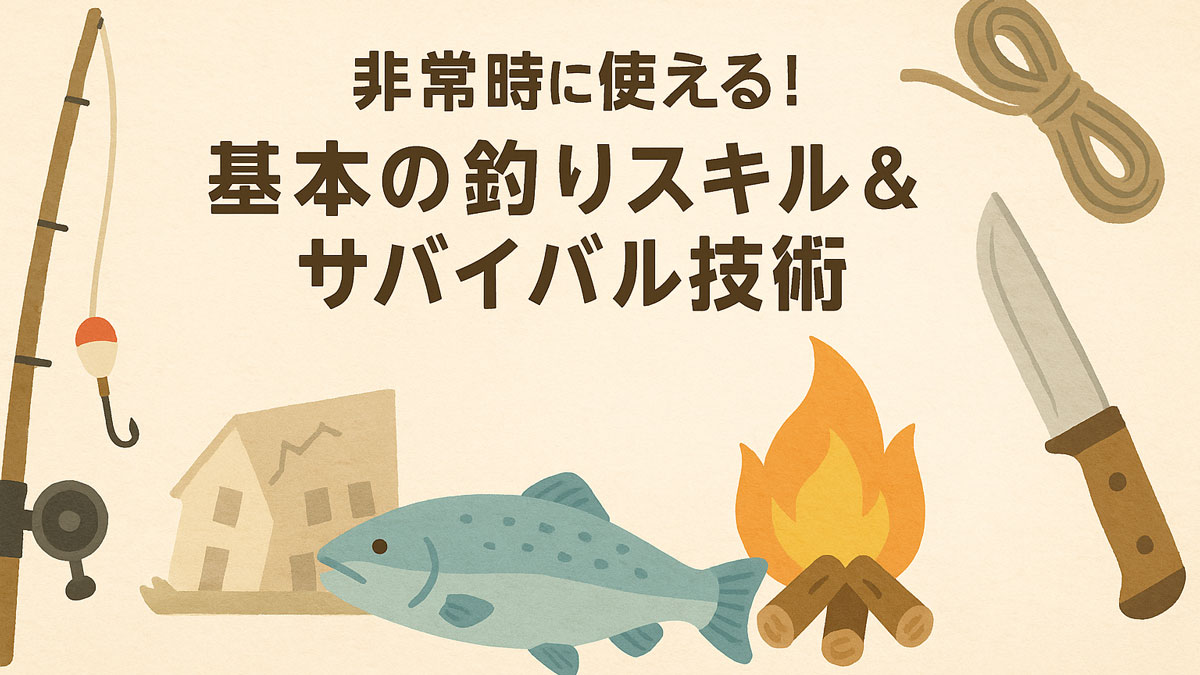
身近なもので作れる「簡易釣具」の作り方
釣り竿やリールがなくても、身近なアイテムを工夫すれば「即席の釣り道具」は十分作れます。必要なのは、針の代用品・糸・竿の3つだけです。
-
針代わり:安全ピン・クリップ・画鋲などをペンチや石で加工。先端を曲げればOK。
-
糸代わり:ビニール紐、ミシン糸、靴ひもなどで代用可能。
-
竿代わり:木の枝や、壊れた傘の棒などを使用。
これらを組み合わせるだけで、川や池で小魚を釣ることは十分可能です。
重りがない場合は、小石を布で包んで糸の先にくくる方法も有効です。
また、エサはパンくず、米粒、虫など、現地調達できるもので対応できます。特に、ミミズやバッタなどの昆虫は、ほとんどの淡水魚に効果があります。
釣れる魚の見分け方|食べられる魚・注意すべき魚
釣り上げた魚が「食べて安全かどうか」は、命を守る上で非常に重要な判断ポイントです。以下に、よく見かける魚の安全性をまとめました。
| 魚の種類 | 食用可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| フナ | ○ | 泥臭い場合は血抜き・内臓処理必須 |
| ブルーギル | ○ | 外来種だが加熱すれば可食 |
| ハゼ | ◎ | 淡白で美味、安全性も高い |
| ウグイ | △ | 寄生虫の可能性。必ず加熱 |
| ドクウツボ等 | × | 有毒種は絶対に食べない |
「生での摂取」は絶対にNGです。淡水魚には寄生虫リスクがあり、加熱処理が基本。特に内臓はしっかり取り除くことが必要です。
判断が難しい場合は、ヒレが鋭くない/臭いがきつすぎない/派手すぎないという特徴を覚えておくとよいでしょう。なお、初めての地域で釣った魚は、必ず加熱を前提としてください。
火起こし・魚の下処理・調理法の基本
魚を釣った後は「火を起こし」「内臓を処理し」「安全に食べる」工程が待っています。
-
火起こし:ライターがなくても、乾いた草・新聞紙・木の枝などがあればマッチ1本で火が起こせます。反射板(アルミホイル)を使うと効率UP。
-
下処理:うろこを落とし、内臓を取り除き、血合いを洗い流す。ナイフがない場合は、缶詰のフタや釘、硬貨などを工夫して代用可能です。
-
調理法:串に刺して直火焼き。皮ごと焼けば、表面がバリアになって中まで火が通りやすいです。塩があれば保存性・風味が向上します。
火と刃物を安全に扱う技術は、釣りだけでなくあらゆる非常時対応に役立つ“ライフスキル”です。
また、調理後に残った骨や内臓も無駄にせず、魚の骨スープなどに活用すれば、栄養価を高められます。
まとめ
非常時において「釣り」は、食料を確保し、生き抜くための重要な選択肢になります。身近なもので工夫する力、食べられる魚を見極める知識、そして調理までの一連の流れを知っておくことで、レジャーが“サバイバル力”に変わるのです。
次回は、具体的な「防災バッグに入れておくべき釣り道具」や「キャンプと防災の共通装備」などを紹介予定です。
3. 防災に活かせるおすすめ釣りアイテム7選【持ち出しOK】
災害時の「備え」として、非常食や水、医療用品に目が行きがちですが、実は釣りアイテムも防災リュックに入れておくと心強い道具のひとつです。
釣り道具には、食料確保だけでなく、火起こしや工作など多目的に使えるものが多数あります。ここでは「防災兼用」で使えるおすすめの釣りアイテム7つを厳選して紹介します。
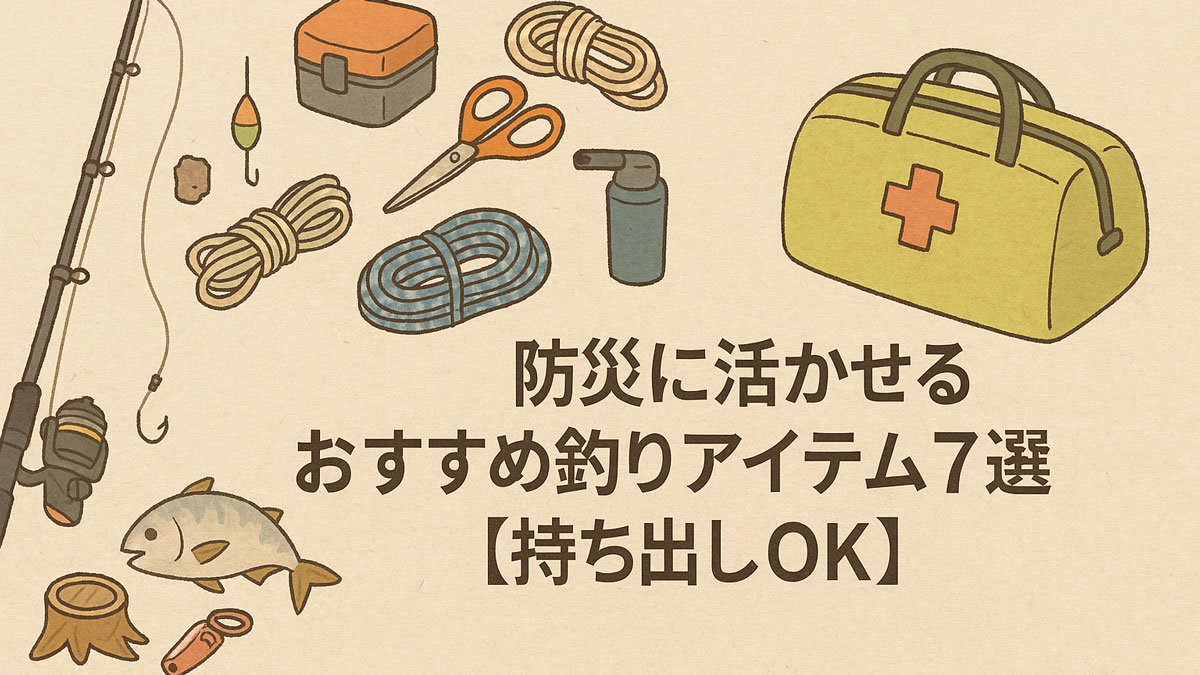
収納しやすくて汎用性が高いコンパクト道具
釣り道具は一見かさばりそうに思えますが、コンパクト設計のものを選べば、リュックの隙間にも簡単に収まります。特に以下の3つは、防災にも最適です。
① コンパクトロッド(振り出し式の小型釣竿)
折りたたむと30cm程度になるタイプが多く、軽量で持ち運びにも便利。非常時には「川・用水路・港湾部」などの水辺で活躍します。
② ミニリール+道糸セット
超軽量で、リール+道糸がセットになっている製品なら、初心者でもすぐに使えます。エサさえあれば即座に釣りを始められる点で、サバイバル力が高いツールです。
③ 小型タックルボックス(仕掛け+針セット)
針、オモリ、仕掛けなどをまとめて収納できるミニケースは、防災リュックのポケットにも収まります。釣りだけでなく、針金やフックとしても転用可能。
ロープ・ハサミ・携帯火器…釣りでも防災でも活躍するギア
釣りに使う小物の中には、「非常用ツール」としても優秀なものが多数あります。
④ 多用途ロープ(PEライン or パラコード)
軽くて強度があり、数十メートル巻かれているので、「縛る・吊るす・つなげる」などさまざまな用途に使えます。テント固定や滑落防止にも活用できます。
⑤ 釣り用ハサミ(カラビナ付き)
ラインカット専用のハサミは、小さくても切れ味抜群。ガーゼのカットや応急処置、パッケージの開封など、防災現場で大活躍します。
⑥ 火起こしアイテム(マグネシウム着火棒)
最近のアウトドア用火起こしアイテムは、釣りブランドからも多数登場。濡れても使える火打ち石タイプは、雨の日の災害時にも重宝します。
⑦ ヘッドライト(防水+赤色ライト対応)
釣りの夜間作業に欠かせないヘッドライトは、防災時の停電対策にも最適。手が空くため、安全な作業や夜間移動に役立ちます。
【まとめ】釣りアイテムは“災害時の万能道具”になる!
下記に、紹介したアイテムを防災用途別に分類した表を掲載します。
| アイテム名 | 主な釣り用途 | 防災時の活用例 |
|---|---|---|
| コンパクトロッド | 釣り | 食料確保 |
| ミニリール&道糸セット | 釣り | 食料確保 |
| 小型タックルボックス | 仕掛け収納 | フック・道具入れ |
| PEライン・パラコード | 仕掛け作成 | 縛る・結ぶ・補修 |
| 釣り用ハサミ | 糸切り | 応急処置・作業用カット |
| 火起こし棒 | 野外炊事 | 暖房・調理・SOS発信 |
| 防水ヘッドライト | 夜釣り | 停電時の行動・照明 |
これらのアイテムは、レジャーとしての釣りを楽しむ中で、そのまま“防災訓練”にもなりえる優れものです。家族で釣りを楽しみながら、防災意識を高めるというアプローチも非常に効果的です。
次回は「水辺での安全対策」について詳しくご紹介します。防災としての釣りを考えるなら、装備だけでなく“危機管理意識”も忘れずに備えましょう。
4. 釣り場での安全対策|水辺での事故を防ぐために知っておくべきこと
防災として釣りを活用する際、最も大切なのは「安全」です。どれだけ道具があっても、水辺での事故やケガがあれば元も子もありません。
ここでは、自然災害後やアウトドアでの非常時において「命を守るための水辺でのリスク回避術」をご紹介します。

増水・流れ・ぬかるみ…危険予測の基本
災害直後や大雨の後に川や海で釣りをする際、まず最初に確認すべきなのが「水位」と「流れ」です。特に川釣りでは、前日の降水量やダムの放流状況によって、急な増水が発生することがあります。
普段は穏やかな水辺でも、わずか10分で濁流に変わることがあるということを常に意識して行動することが大切です。
また、以下のような“足元の変化”にも注意が必要です。
-
ぬかるんだ土手:足を取られて転倒、川に転落する危険
-
崩れかけた護岸ブロック:一見安全そうでも、不安定なことが多い
-
濡れた岩場・テトラポット:滑りやすく、大人でも転倒しやすい
「水辺に近づく=命に関わるリスクがある」という意識を持つだけで、判断力と危機回避能力が格段に高まります。
特に子どもと一緒に釣りをする場合は、先に安全な動線を大人が確認することが基本です。急に流れが速くなった、水の色が変わった、という場合はすぐにその場を離れるようにしましょう。
ライフジャケット・サバイバルホイッスルの重要性
万が一の「落水」や「遭難」に備え、最低限持っておきたいのが以下の2つの安全装備です。
① ライフジャケット(フローティングベスト)
水難事故の致死率を大幅に下げる装備です。最近では、釣り用に軽量・コンパクトな製品が多く、防災リュックにも常備可能。おすすめは「自動膨張式」または「手動膨張式」のタイプで、着たまま動きやすく、持ち運びも苦にならない仕様が主流となっています。
特に海や深い川では、泳げる人でも想定外の事故が起こります。自己判断に頼らず、全員が装着することを原則にしましょう。
② サバイバルホイッスル
これは“声の代わりに助けを呼ぶ”ための道具です。水辺では風や波音で声がかき消されやすく、呼びかけが届かない場面が多発します。ホイッスルなら、軽く吹くだけで100m先にまで届くこともあります。
特に以下のような状況で有効です。
-
落水して手がふさがっているとき
-
視界不良(夜間・霧など)で仲間とはぐれたとき
-
怪我や脱水で声を出すのが困難なとき
災害時には通信手段が使えないこともあるため、ホイッスルは“原始的な命綱”ともいえる存在です。
【まとめ】安全こそが防災×釣りの土台になる
釣りが防災に役立つのは事実ですが、それも安全が確保されてこそ。水辺に潜むリスクは、一瞬の油断で命を奪います。
以下に、安全対策の優先度をまとめた表を掲載します。
| 危険要素 | 事前に確認すべきポイント | 対策アイテム例 |
|---|---|---|
| 増水・濁流 | 前日の雨量・川の色や流速 | 雨天アラートアプリ、水位情報サイト |
| 滑落・転倒 | 足場の状態、濡れた岩・ぬかるみ | グリップ付きブーツ、トレッキングポール |
| 落水・遭難 | 水辺の深さ、周囲の人の位置 | ライフジャケット、ホイッスル |
防災のために釣りをするなら、まずは「命を守る行動」が前提です。安全装備は“最後の手段”ではなく、“最初に備えるべき道具”として意識しましょう。
5. 【まとめ】釣りは最高の“備え”になる!自然の恵みを生かす力を身につけよう
防災と聞くと、どうしても「備蓄」「避難用品」「情報収集」が中心になりがちです。もちろんそれも大切な備えですが、もうひとつ忘れてはならないのが“生き抜くための力”です。
その力のひとつが、自然から食を得る「釣り」という技術。単なる趣味にとどまらず、家族を守る手段にもなりうるのが釣りの真価です。
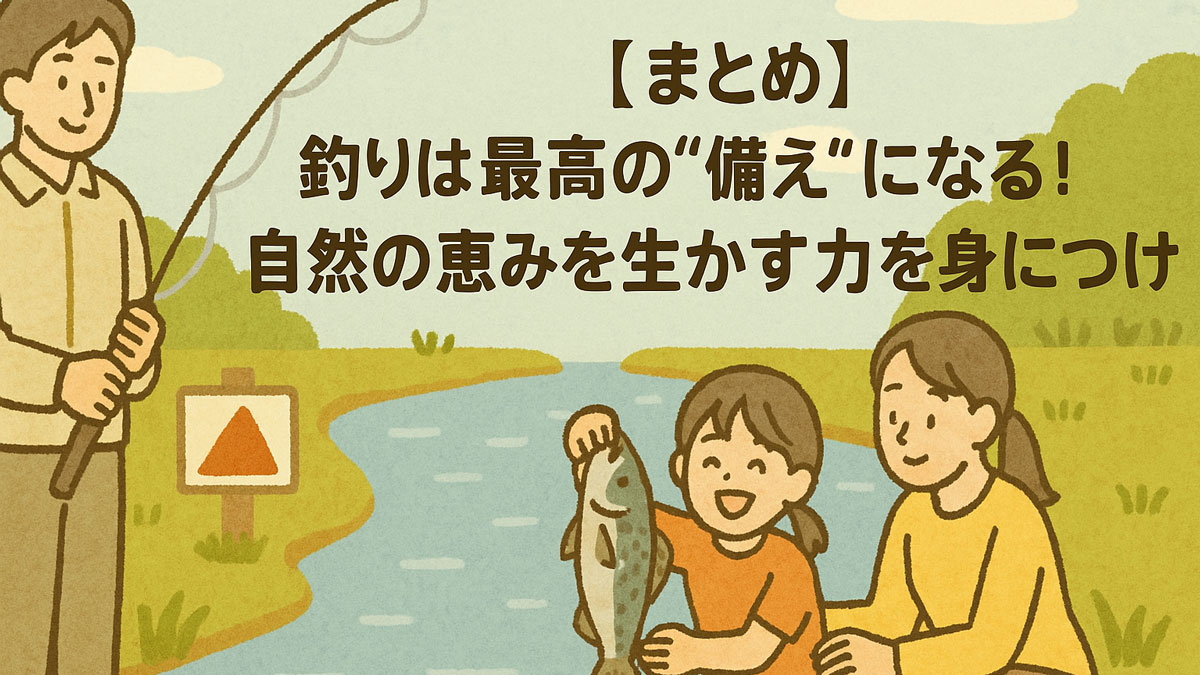
釣り経験が「家族を守る力」に変わる
釣りは一見「のんびりしたレジャー」に思えるかもしれませんが、実は多くのサバイバル要素が詰まった行動です。
-
獲物を探し、仕掛けて、捕まえる
-
環境を見極め、安全を確保する
-
調理して食べることで命をつなぐ
これらは、災害時や非常時に必要とされる“行動力・判断力・技術力”そのものです。
特に小さな子どもや高齢の家族がいる家庭では、「食料を自力で得られる人」がいることが、精神的な支えにもなります。
釣りに慣れていれば、地元の水辺の特徴や釣れる魚の種類、危険箇所なども把握できます。それは、いざという時の「地理的知識」にも直結します。
日常の趣味が、いざというとき命をつなぐ
釣りの魅力は「楽しさ」と「実用性」が両立していることです。
例えば、家族で休日に釣りに出かければ、
-
子どもは自然のしくみや食物連鎖を学べる
-
大人はアウトドア技術を身につけられる
-
家族全員で防災スキルを“体験的”に学べる
というように、防災教育にもなります。
さらに、以下の表に示すように「趣味」としての釣りが、そのまま「命を守る行動」に変わる例は少なくありません。
| 日常の釣りスキル | 非常時での応用 |
|---|---|
| 魚を釣る | 食料の確保 |
| ナイフや火の扱い | 自炊・煮炊き・暖を取る |
| 水辺の危険察知 | 増水や滑落事故の回避 |
| 地域の釣りスポット知識 | 安全な避難場所・物資調達エリアの把握 |
こうしたスキルを普段から「遊び」として身につけておくことは、いざという時に大きな違いを生みます。釣りは、自然の恵みを活かし、命をつなぐ“知恵”と“力”を育てる最高の準備方法なのです。
おわりに|“もしも”に備えるなら、まず“楽しむ”ことから
「防災=備蓄や避難」だけでは、対応しきれない状況があることは、過去の災害からも明らかです。
“自然の中でどう生きるか”という視点が、これからの防災には欠かせません。
その第一歩として、「釣り」を趣味として始めてみるのはいかがでしょうか?
食料、道具、知識、安全、そして人とのつながり——釣りを通して得られるものは、想像以上に多く、深いはずです。
楽しく、学びながら、“いざ”に備える。
それが、最も無理なく続けられる「サステナブルな防災」の形です
出典・参考文献:
-
内閣府「災害に備える」防災情報のページ
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/index.html -
消費者庁「食品の備蓄と災害時の栄養」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/disaster_prevention/ -
国土交通省「河川の危険箇所・水位情報」
https://www.river.go.jp/ -
日本釣用品工業会「初心者のための釣り安全ガイド」
https://www.jsyia.or.jp/